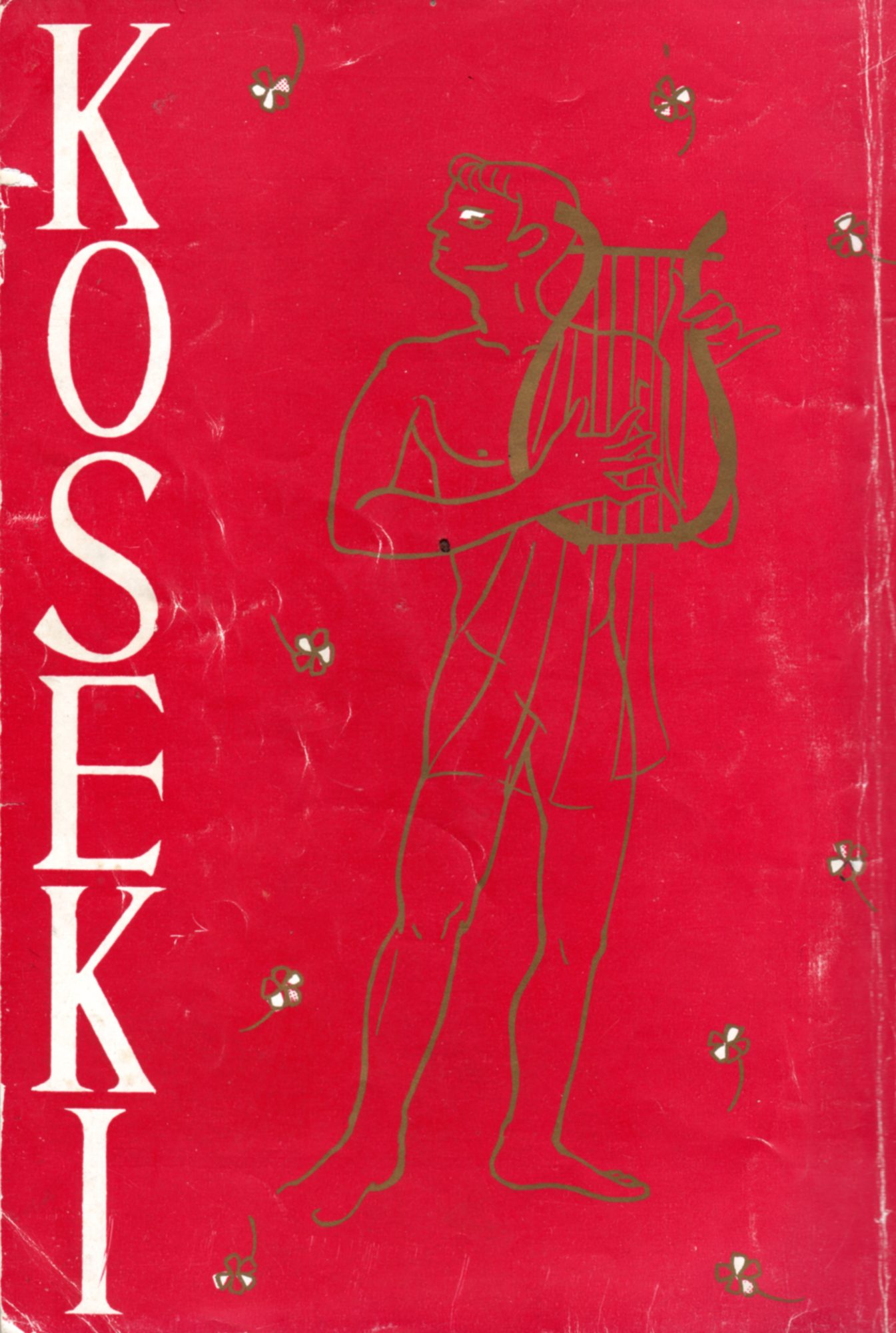
在学中の学校誌「航跡」11号をアップします
私たちが高三の時の1960年に発行された「航跡」11号を天本さんがお持ちでしたので、お借り出来ました。1960年は激動の60年安保闘争の年でした。皆さんしっかりと考え、表現されています。それをテキストファイルにしてホームページにアップすることを思いつきました。下のリストのように、私達9期生は19名、1年下の10期生が13名、11期生20名、先生方7名の作文が載せられています。テキストファイルにするのは大変な作業ですが、9期生の作文を1組の人の分から始め、順次アップしていこうと思っています。アップするのに執筆者の了承を得るのがいいとは思いますが、この「航跡」の投稿文は公開を前提に推敲され、編集をして頂いた先生方の点検も受けていますので、明らかな誤植部分の訂正をする以外は原文通りアップさせて頂くことをご了承下さい。(自分の文章を載せて欲しくない、という要望がある方については削除させて頂きます)ご自分の約60年年前の作文を読まれての、感想やコメントがありましたら、メールなどでお寄せ頂ければ、それも紹介させて頂きます。先生方や下級生の作文については、それを読みたいという希望がありましたらお聞かせ下さい。その希望のある作文については頑張ってアップしていきたいと思います。「航跡」9号、10号をお持ちの方はお貸し下さるようお願いします。それも見つかり次第、頑張ってアップしていきたいと思います。 2020.11.29. 管理人
先生方
| 八束周吉先生 「高校自治会の倫理」 |
| 中村止戈男先生 「「時局に思う」 |
| 織田省三先生 「大阪と近世文人たち」 |
| 神楽岡昌俊先生 「漱石の自己本位の立場」 |
| 赤井 逸先生 「サイバネティックスとライプニッツ」 |
| 中川 貴先生 「雑感」 |
| 市川 洋先生 詩「熊」 |
生物部プランクトン班 大阪城濠のプランクトンの研究
9期生(1960年 3年生)
| 1組 中野儀人 「犯罪と善性について」 |
| 1 片岡健太郎 「宗教の本質」 |
| 1 雪本 (博) 「マス・コミュニケーションのあり方」 |
| 1 傍士研一 「ヒューマニズム」 |
| 2 天本登志子 「孤独と人間嫌い」 |
| 2 木下睦美 「愛国心について」 |
| 2 松原秀文 「幸福について」 |
| 2 野原 忠 「ヒューマニズムについて」 |
| 2 村林正策 「ヒューマニズムについて」 |
| 3 平尾泰朗 「信じるということ」 |
| 3 入江脩二 「民主政治について」 |
| 3 安藤利子 「人間として」 |
| 3 滝口勝久 「ヒューマニズムについて」 |
| 4 亀田寿子 「涙の英知」 |
| 4 松村泰輔 「神とクセノパネス」 |
| 4 中尾英一 「自意識」 |
| 4 近藤美智代 「ヒューマニズムの倫理思想」 |
| 4 谷沢佐代子 「我が国に於けるヒューマニズムの在り方」 |
| 4 国分重昭 ヒューマニズムと古典」 |
10期生(1960年 2年生)
| 1組 | 門川江都子 「逃げる」 |
| 1 | 吉沢邦夫 「宗教」 |
| 1 | 待井隆志 モーム「人間の絆」 |
| 1 | 佐谷 弘 「独歩の詩想について」 |
| 1 | 原田紘子 「思うこと」 |
| 1 | 新野七七子 「ひととき」 |
| 1 | 笠井照子 「生きる喜び」 |
| 1 | 寺田貞子 「槍岳登山」 |
| 1 | 吉沢邦夫 詩「追高応援歌」 |
| 2 | 平康尚美 「一人称の私」 |
| 2 | 浜納御幸 「日記の中から」 |
| 2 | 元井文代 詩「海と空と潮風と」 |
| 2 | 小林典子 「小さな幸福」 |
11期生(1960年 1年生)
| 1組 | 川島倫子 「私のノート」 |
| 1 | 仁保淳子 「一輪のマーガレット」 |
| 1 | 中村佐保子 「満員電車の中で」 |
| 1 | 田遠洋子 「ちっちゃな女の子」 |
| 1 | 小村貫子 詩「幼稚園時代の友」 |
| 1 | 米沢武敏 「大阪城周辺の風物」 |
| 2 | 高森 優 「私」 |
| 2 | 畑田英明 「趣味」 |
| 2 | 木谷功七郎 「朝の地下鉄」 |
| 3 | 島田 清 「ヘラぶな釣り」 |
| 3 | 永谷孝雄 「母校の先生」 |
| 3 | 山西允彦 「或る作文を読んで思ったこと |
| 3 | 秋武啓子 「しゅろの木によせて」 |
| 3 | 松本多美子 「帰らぬ父」 |
| 4 | 服部浩子 「自分の道」 |
| 5 | 数井百合子 「春の朝」 |
| 5 | 本田 稔 「祖母」 |
| 5 | 永井邦世 「雨の日に」 |
| 5 | 内藤ますみ 「朝の電車」 |
| 5 | 山口道代 詩「夜」 |
学年不明
| 武智健照 詩「たそがれの浜辺に」 |
| 泉 保和 「顔」 |
| 水田孝男 「死」 |
織田省三先生 「大阪と近世文人たち」
織田作之助の「夫婦善哉」に始って、「暖簾」とか、「ぼんち」とか、或いは最近「がめつい奴」と言った大阪物が小説界や演劇・映画方面で一寸したブームを起しているが、これらの作品に共通する大阪人特有のねばりっこい強烈なリアリズム精神の発祥時である近世にスポツトをあてて、西鶴を中心としたいろいろな文人達に触れてみたい。
その前に簡単ながら大阪の歴史をたぐって見よう。大阪は古くは「なにわ」と言って難波の文字をあてており、仁徳・孝徳・聖武の三代の帝都であり、この点においては京都より歴史が古いわけである。仁徳夫皇は高津の宮、孝徳天皇は長柄豊碕の宮、聖武天皇は難波の宮を各々営まれたのであるが、これらの宮殿はいずれも馬場町にある大阪中央放送局の東裏側から赤十字病院にかけてのものであって、特に難波の宮の方は最近の発掘によりその位置が一段と明瞭化されているようである。このように一時帝都として栄えた「なにわ」も恒武天皇十二年(一四九六)蓮如上人が、かつての宮殿跡に石山本願寺を建立したことに始まる、やがて同寺を中心とした寺内町が出来、多くの信者がそこに集住し、門前町として大阪は発達の糸口を開いたのであった。この本願寺は火災の為惜しくも焼失したが、全国を統一した豊臣秀吉が上町台地の南端に大阪城を築き、いよいよ大阪発展の足場を固めたのであった。だが秀吉歿後またまた大阪は戦乱の地と化し、秀吉によって都市としての形態を持ったこの地は無茶苦茶に破壊され、住人達は霧散してちった。秀吉に代って天下の実権を把握した徳川もこの地の重要性をよく考え、秀吉以上の努力を払って荒廃したこの大阪を復興し拡張し、大商業都市としての町造りに成功したのであつた。そして文化的には全く疎遠の地であつたこの大阪に、漸く文化の花咲く時期が来たのである。これを文学の面より見れば、先ず国学、俳諧、浮世草子、前期読本と言ったものである。
<契沖>
先ず国学者契沖の話から始めよう。国学とは言うまでもなくわが国の古典を研究し、古代精神を探究する学問である。契沖は尼ケ崎の生れであるが、十一歳の時より父母の許を離れ大阪の今里にある妙法寺に入り仏学を学び更に高野山にも登り本格的に仏学を修めて後、彼を国学者としての目を開かせた下河辺長流と言う得難い友を得た。その後いろいろな紆余曲折を経て四十歳にて彼が幼少時世話になった今里妙法寺の住職になった。彼の代表的な「万葉集代匠記」の草稿もこの寺で起している。これは万葉集の研究書としてまことに貴重なものであり、今日に至るもこの書の価値は失われてはおらない。だが寺の住職では思うように仕事もはかどらなかったが、しかるべき後援者があって、この寺は弟子に譲って円珠庵に隠棲し思うように仕事の出来る環境を得たのであった。彼がここに入所したのは元祿三年の五十一歳で、歿した六十二歳まで十年余古典の研究に没頭した。この間万葉集や古今集の註釈やその他の古典の講議等彼の残した仕事には枚挙にいとまないぐらいである。さて、この契沖が晩年過した円珠庵の位置と言えば、上本町四丁目の市電停留所に交叉している道を東へ二・三丁進めば明星学園の手前左側にこの円珠庵がある。ここも一時廃墟同様になっていたのであるが、戦後大阪在住の国文学者達によって復興され、今日も契沖を偲んで、国文学の講座が現代もこの円珠庵においてさかんに行われている。

<井原西鶴>
さて次ぎには最も大阪人らしい文人井原西鶴であるが、西鶴こそ生粋の大阪人であり、商家の出身で町人生活を身を持って体験し、金をめぐる町人のすさまじい動きを、たくましいリアリズムの眼をもって書きまくった偉大な作家である。西鶴の作品は今や諸外国間にも相当な関心と反響を呼び、西鶴研究の為に来日する熱心な外人もかなりある。日本の近代作家においても、森鴎外・幸田露伴・樋口一葉・尾崎紅葉・田山花袋・志賀直哉・菊池寛・宇野浩二・尾崎一雄・武田麟太郎、織田作之助等、彼に心酔している作家がかなり多い。これらの作家達は彼等の小説や評論や随筆において口を極めて西鶴の偉大さを賛仰している。
西鶴は最初は談林派の総帥西山宗因門下の俳諧師として活躍したが、晩年浮世草子作家として異名をはせたその文才は、俳諧師時代から遺憾なく発揮されていたようである。その一例として矢数俳諧に関してのことを話そう。矢数俳諧とは限られた時間内に独吟してその句数の多きを誇ると言うゲームの様なものであって、それがその当時流行し、一流の俳諧師達が各々記録更新を目指し競争し合ったのだが、西鶴もその例に漏れず幾度かこれを行い、抜きつ抜かれじの成績を続けていたが、彼四十三歳貞享元年(一六八四)の六月五日住吉神社の社頭で一昼夜ぶっ通して二万三千五百句と言う他の追従を許さぬ快レコードを達成した。一昼夜に二万三千五百句と言えば一句の持ち時間三・三秒で全く超人的な事と言わねばならない。ところがこの興行は口述があまりにも早くて速記がとれず作品が残っていないのでこの快挙の真偽の程も疑われたのであったが、これを証明する当時の色々な書き物が残っていて西鶴専門の研究家間では真実視されている。世間の人々はそれまで阿蘭諧(おらんだ)西鶴(西鶴の俳諧の新風をけなしてつけた異名)と呼んで見下げていた彼にも二万翁と言う尊敬すべき異名が改めてつけられている。
ところで西鶴の真の文才は、この俳諧ではなく浮世草子と呼ばれる一連の小説に発揮されている。従来の日本文学に例を見ない肉欲的愛欲的な好色物や、金銭の渦中にある人間の動きを把えた町人物等、西鶴の作品は現実の本当の姿を凝視するところより生まれた作品である。俳諧師であった彼が小説家に転向したのは天和二年四十二歳の折で、従って彼が本格的に小説に熱中したのは晩年の十年間であった。その間妻を亡くし一人の女児も失い、彼自身も病魔に襲われた不週の晩年ではあったが、彼の強力な敬文精神のみは、燃え上る炎より激しきものを持っていた。特に町人物の「日本永代蔵」「世間胸算用」「西鶴置土産」においては早期資本主義勃興期のたくましい大阪町人の赤裸々な姿を残すところなく描いている。「がめつい奴」の「おしかばあさん」も顔まけする人間がいくらも登場する。資本蓄積の為だが、西鶴は金銭の虜になった人間の姿を描くのみでは終らなかつた。最後の「置土産」においては金銭に負けない人間性への追求にまで筆が及んでいる。上本町六丁目と四丁目の中間に電車道に沿ってある誓願寺にこの西鶴の墓所がある。「仙皓西鶴」と風雅な大きな文字で刻まれているこの墓はいかにも西鶴にふさわしいものである。
<芭蕉>
次ぎに芭蕉であるが、彼は勿論伊賀上野の出身であったが偶々大阪が彼の終焉の地となり、その意味で大阪と関係深い人となっている。元禄七年五月九州旅行を画して江戸を出発し、途中故郷に寄ったりあちこちでの俳諧の興行に参加したりして大阪にやって来たのは同年九月九日の夕べであつた。ところが旅のつかれか病に犯されるところとなり、而もこの病は日増しにつのるばかり、大阪の弟子達は大いに狼狽し十月五日南御堂付近の花屋仁右衛門の裏座敷に芭蕉を移した時はもうかなりの重態であった。大阪の弟子達の報せによって、京都膳所、大津方面から高弟達が続々と集まって来た。だが弟子達の介抱も空しく十月十二日
旅に病んで夢は枯野をかけめぐる
の辞世を最後に詩聖は五十一歳の生涯を終った。この臨終記は門人其角の「枯尾華」、同じく支考の「笈日記」に詳しく記されている。前年には西鶴が歿し、又続いて芭蕉と巨星相続き落ち、明るかった上方の空も次第に曇って行く様相となった。その夜、弟子達は芭蕉の遺言通り遺骸を大津の義仲寺に葬るべく八軒屋(現在市電の天満と天神橋の間、戦前はここにも市電の停留所があった。またここは大阪・伏見間の船つき場として繁盛したところ)から船で送られたのであつた。さて花屋仁右衛門なる人の裏座敷がどの辺にあったかは明瞭ではないが、地下鉄本町駅を出た所の御堂筋を二丁程南へ行った東側に(自動車通路と自転車道の間にある街路樹のかげに)「此付近芭蕉翁終焉の地と伝ふ」と刻まれた石くいと、先程の辞世の句碑が立てられている。

<蕪村>
芭蕉歿後二十三年目(一七一六)に蕪村が誕生した。無村の家柄や父母の名も伝わらない今日ではあるが、近来の研究によって摂津国東成郡毛馬村、即ち大阪市旭区毛馬町が蕪村の出生地であることが確認されている。現在毛馬町有志の人々によって有名な毛馬の閘門付近に「俳聖・蕪村之顕彰碑」というのが建てられている。蕪村がこの故里を離れて江戸に出たのは十六、七歳或いは二十歳とも言われているが、江戸を始め各地を流浪して俳諧と画を学び一生涯郷里に再び寄りつかなかった。従って無村は唯大阪の生まれと言うことのみであるかと言うとそうではない。故里を恋いつつ故里に帰れなかった蕪村の心境がいくつとなく作品に出てくる、詩人萩原朔太郎氏の名著「郷愁の詩人与謝蕪村」に右の事がよく解明されている。土蔵などのあつた実家を偲んだ
柚の花やゆかしき母屋(もや)の乾隅(いぬゐずみ)
や、幼少時女友達を思い
妹が垣根三味線草の花咲きぬ
の句や亡き母への侘びしい思慕を藪入りの少年に託して
藪入の夢や小豆の煮えるうち
等、蕪村作品の底を流るるこのロマンチシズムは郷愁に外ならないと萩原氏は説いている。さてこの郷愁が最も強く出ている作品は彼が六十歳という老齢にありながら懐旧の念去り難く作った「春風馬堤曲」であろう。
やぶ入や浪花を出て長柄川
春風や堤長うして家遠し
に始まるこの長詩はまことに現代詩を思わせる新しい形式の作品出、一人の少年がつとめ先の主家から藪入りで休暇を貰って喜々としてこの淀川の堤を通って懐しい母親許へ帰って行く過程を詩的に表現したものだが、この少年の心情こそ年少時にして両親を失い、家を失い、故郷を去った蕪村の心の底よりうめき出た作品は外ならない。この作品は現在使用している古文の教科書「古典三」に出てくるのでその学習の折よく鑑賞してもらいたい。
さてその外、近世時代大阪に縁の深い文人としては西鶴の師であつた西山宗因や、同じく談林俳人の小西来山、前期読本作家の上田秋成、人形浄るり作家として有名な近松門左衛門等実に多士済済であるが、これらの人々についてはいずれ語る時もあるだろう。
神楽岡昌俊先生 「漱石の自己本位の立場」
漱石は英国留学一年にして、「自己本位」の立場を「多年の懊悩した結果漸く自分の鶴嘴をがちりと鉱脈に掘り当てたような気」で摑むことが出来た。それは英国にあっての、英文学の研究や、日常生活より得たものとも見られようが、その自己本位の立場というものが、先ず漱石に摑まれたのである。そこに、「安心と幸福」とを見出したのである。それ等は、彼の国の文学と、彼の文学観との相違から発して、漱石自身が「一個の日本人であって、決して英国の奴婢でない以上」受け売りでない「正直」な態度から文学を定義しようとして得られたものである。かようにして、今までの「浮華を去って摯実に就」くことが始められた。然し、それは、文学という学問の世界に大成されると云うよりは、帰朝後の創作生活に大きな結果を招来した。大正三年末の講演の中に、「其の時、得た私の考は依然としてつづいています。否、年を経るに従って段々と強くなる」(私の個人主義)と言っているのを見れば、大正五年「明暗」製作前後の「則天去私」の大文字に到る迄、この個人主義と云うより、理想的な個性発揮主義の考が、発しつづけていたものと考え得るだろう。
漱石の全作品を考えて見ると、すべて「私」の人が主題となって、展開されている。しかも、その夫々の作品は、自己本位の立場を持している漱石の人となりを表すものである。一体漱石の作品は、理屈の多いもので、またそこに魅力も在るものであるが、それ等は皆、「私の個人主義」に表れた漱石の表れなのである。 それは、自己本位の立場の淋しさである。これは決して西欧にはないと思われる自己本位の思想であろう。一体人間の行為は、自己の不満不安、罪、矮少の意識から、言わば心理学的な生活空間の場の動揺を安定させよう、満たそうとする通路として考えられる。漱石がこの淋しさを朗かな面に展開しようとするのは、この様に説明出来そうである。しかし、この「厭わしい」世を、自己本位の立場から、安心しようとしても、盲目の意志、生きんとする意志のために遂に安心が得られないのである。漱石が、「死んだら柩の前で萬歳を称えて呉れ」る様にと言っていた気持もここから判る様な気がする。漱石はこの「私の個人主義」なる論で、個性の発揮、権力、金力の行使に伴う制約としての責任(義務)の道徳的要求に言及し、それがそれ等三つの背後にある人格に俟つべき事を要求している。所謂「職業学」といったものの必要を言っている。当時として、最も早く、日本の市民的自我の発見をした漱石が、又鋭敏な頭脳に、この個人主義の普遍的に発展する場合の「危険」を感じて いた結果が、あの初期の諸作品に表れている正義感なのである。「猫」の最後の章で、作中人物の個性を見失っていると門弟に評される程、この個人主義の弊害を述べているのは、如何に漱石が、社会に働きかける事に急を感じていたかが判るのである、しかし、私が最も切実に感ずるのは、漱石がひるがえって、自己本位の淋しさを切り抜けようとしている所である。討死をも辞せない志士的覚悟を作家に要求した漱石と共に、文士を押すのではない人間を押すのだと忠告した漱石が有難いと思うのである。
漱石の全作品は漱石一流の解決が与えられてはいるが、作中人物同志と同様に、独語的な点がある。それは「ことば」というものの表現能力が、一般的概念にしか出来ないのと、漱石が知性作家といわれる所以と、また、自己本位の淋しさを物語るものなのである。
個人主義というものは、倫理的に言って、自然性の満足を意味し、他の干渉を少くしようとする利己主義的なものと、その理想的な個性実現を意味し、それへの妨害を除去しようとする個性主義に二分出来るのではなかろうか。今こう仮定すれば、前者は社会に転じて、社会を自己本位に改める傾向が強いが、後者は社会を自己本位で蔽うというよりは、自己本位の中に淋しく生きて行くという方向を採るものである。漱石も「何だか個人主義と言うと一寸国家主義の反対で、それを打ちこわすように取られますが、そんな理屈の立たない漫然としたものではないのです」と言っている。この立場の説明として、漱石はこの二者の関係を寒暖計にたとえて、「各人の享有する自由というものは国家の安危に従って上ったり下ったりする」のだと言い、「是は理論と言うよりも寧ろ事実から出る理論と言った方がいいかも知れない」と言い、「事実出来ない事を国家のためにする如く装うのは偽りである」と言う「正直」な態度を表明しているのである。他に示して強要すると言うより、自分の生活態度なのである。
せっぱつまった事として、何事も露骨に書く事を本性上嫌った漱石は、なかなか自分を全面的に表せない愧(くや)しさを持っていた。この愧しさから来た心のゆとりと、漱石の思念的であった事から、あの初期の「おかしさ」が出ていると考えられる。会話と言うものが人の間柄という場面に於て行なわれる行為で、理論理屈はそこに成立して来るのであるが、漱石のそれは、いつも漱石の立場を他が許さないで、「党派心」にとられて、「理非」を持って許し合わないという現実を意識せねばならなかった。当時の自然主義思潮の様に、観念を排して専ら対象に立脚するのではなく、理想を行なうに現実を以てするという方法を本性上有していた漱石はこの様な現実をしか見ざるを得なかったのである。こうして漱石は、舒述的弁解的となって行くのであった。それが此の「個人主義」に於ても、「私のような詰らないものでも自分で自分が道をつけつつ進み得たという自覚があれば、あなた方から見て其道が如何に下らないにせよそれは貴方方の批評と観察で私には寸毫の損害がないのです。私自身はそれで満足する積で」あると言わざるを得ない「正直」な気持を表わさないでは居れなかったのである。淋しいと言う事が人の動く原因である。現実に切り込もうとする時、対象たる人間及び一般社会が、彼等の標榜する抽象的イズムなるものを振りかざして、自己本位の立場を動揺せしめねばやまぬと知った時、漱石は、ついつい自己を守ろうという道を歩まねばならなかった。そして動けば内部へ内部へと向かうのであつた。当時の外国文化と言うものの影響の激しい時代にあって、一度文学という立場から自己本位の立場を得た漱石は、その淋しさを、名残りの封建的分子でこれを満たそうとする、極めて多い制約を意識する自己本位の立場に帰着した。儒学的制約と言えるものがそこにある。漱石程自己の体験を鋭敏にとり込んで作品に活用している者は案外少ないといわれる。然し、それは、にじみ出た、あの漢詩特有の匂いに似たものであって、漱石も天性写実に秀でないと自白した事を思うと、ますますこの制約されたる自己本位の感を深くするのである。
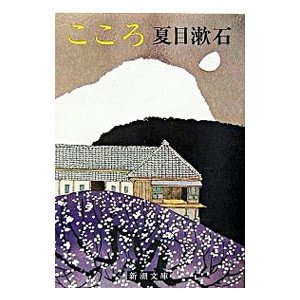
「坑夫」までに表われた人間は殆どが類型的で漱石の鬱憤の表われであった。その鬱憤を慰めるのに猫を水に沈ませ、この世に住めないでその任地を飛び出す「坊ちゃん」、非人情の観照的態度に出て、尚あわれを追う「草枕」の画家(初期の短篇の観照的描写もこれである。)を表わしたのである。また自分も不充分だと自認した「二百十日」の社会への鬱憤、そしてそれを、小説の構想に大きくした「野分」となつて現れた。道也は物質界に重きを置かぬ事と、そう拘泥する立場に立たぬ事を以て解説の方法とする。しかし、後者が勿論高い立場であるがここから趣味の高尚を叫ぶ。これは観照の立場である。これが社会という歯車の油なのである。そして、また理非の世界を強調し、その分を守る事を要求している。「野分」は成長して、「虞美人草」となる。ここには、道也の妻が成長した「我」の女・藤尾となって働く。人の間柄というものを知らない我の女は、第一義の活動によって、血に清められる事となった。自然と、信の天の道が救いとなっている。しかもそれは、倫理宗教というより、儒教の道義の表われの様である。ここに「坑夫」を一つの区切りとして、自己本位の立場が、所謂天とどの様な交渉を来すかを分析し始める。それが「三四郎」からの三部作である。対象が漱石の身辺に近接して描かれ始めるのである。三四郎の自惚れが、美禰子のアンコンシアス・ヒポクリフトへの和解として提出され、美禰子も「復讐は吾に在り、吾是を酬いん」と言うに到る。そして「それから」では、自己本位が天の愛に押されて世の中に入れられなくなり、「門」に到って自己の本位がうづき出すのである。門に立ちつくす人宗助は、天の愛に生きながら、安井の事を妻の御米に告げずにひとりで苦しむ受動者となって、大きな流れに流されて生きて行く人となって終う。ここに作品は自然主義的な色彩を帯び、「彼岸過迄」から漱石のエゴイズムの徹底的な分析となって表れて来る。動き動かされない自己本位とはどんなものであろうか。先ず漱石は動かされる心を動かさない心で観るという立場を求めた。ここに、今迄見て来た諸作品の余裕と、それから出る風流味が生じているのだった。今までの趣味の高尚を叫び社会に警憤を発して独語に終った自己本位の立場は、やはり、人と人との間柄にその本質を見出さねばならず、そうして、再び自己の分析、動かされない自己の確立に志して行ったのである。この動かされないものとして、生物化学的な個体を考えるならば自己を守る立場から自然主義が生ずる。そうすれば漱石の文学は、浪漫的倫理というより、自然的倫理へと成長して来たと言えるだろう。個人を否定的契機としての国家の国家道徳なるものが「辞令はいくら八釜しくっても徳義心はそんなにありゃしません。詐欺をやる、誤魔化しをやる、ペテンに掛ける。滅茶苦茶なもので」あるという国家の「用」を見た漱石には自己本位の立場がいかに高いものであるかを強調せざるを得ないのである。その自然法的社会観からすればかく談じその自己と国家とを程度問題として、「平隠な時には徳義心の高い個人主義に矢張り重きを置く方が」「当然」に思えるのであった。この国家と自己本位の立場と言ったものがこれ以上説明されていないので判らないが、胃潰瘍という生理的に漱石に与える死の問題が如何に漱石に自己の立場を反省させたかは「思い出すことなど」において現れている所である。それは、その平和な気持の永続の望を強く持たしめようとするに到った感謝の心である。「彼岸過迄」はこうして世に出た。
「彼岸過迄」の須永はその天性とも言うべき、内にとぐろを巻く性質で、千代子の「人生のアイロニーを解せざる詩人」振りに、行動に出ない頭の小細工をやって苦しむ。そして、旅に観照の生活を求めて、救われようとするが、それもやはり一時の様な気もする。そうして、「行人」が表われる。この一郎は、絶対の探求者である。一体絶対の探求者がその根下の小草を枯らす事は判るが、彼が人と人との間柄は懐疑して突進し、発狂に到らんとする迄になる心境は、たしかに下界に落ちようとするものである。考え考えて絶対に到ろうとする思索家の一郎はその長所たる知性を短所となってそれを放棄せねばならぬと言う矛盾と人生のアイロニーに屈するかに見える。発狂に近い、観照の絶対に救いを見出すばかりである。信仰と狂気とは死と共に紙一重という所に到っている。この廃墟に立った「心」の先生は、他人の「私」を見て、しかも自分も愛に於ては同じエゴイストである事を知ったのである。「行人」の一郎が妻の人間に、動物的植物的なものを見る事を肯んぜず、温い人間、スピリットを摑んだ時、愛が、エゴイズムの塊りである事を知って、「恋は罪悪ですよ」と言うのである。抽象的な神を論議した昔の生活の代りに一郎は、電車に乗っていて見る市井の一凡人の顔に、頭を下げ、「心」の先生は、奥さんを通して人類に奉仕しようとするのである。先生は「私は未来の侮辱を受けないために、今の尊敬を斥けたいと思うのです。私は今より一層淋しい未来の私を我慢する代りに淋しい今の私を我慢したいのです」と言って、自己の淋しさを認め、こういう所から、来る複雑な原因から、漠然たる不安の中に、明治の精神に殉死する事になるのである。そして先生はその愛に隣るエゴイズムを奥さんに知らせない様にして置くのが人間一般に対する唯一の尊敬と御詫びだと信じて死んで行くのである。こうして今迄よりも一層自然主義的な時代が始まる。それは「道草」である。それは総ての作品に通ずる事であるが、漱石は自分の一作一作を踏み台として、成長して来た人である。十年を経た、自分の帰朝当時の家庭生活を唯一の自伝的小説として書いて、漱石は、自己の自己本位の思想を洗い流そうとしたかに見える。それは、自然主義的描写の中に細い反省の融和が見られるので判る。そこには、現実の中に自己の私をいためつけ、他をかばう態度もにじみ出ているのである。漱石はここまで大きくなって来た。当時の「硝子戸の中」に次の様な文章がある。「自分の馬鹿な性質を雲の上から見下ろして笑いたくなった私は、自分で自分を軽蔑する気分に揺られながら、揺籃の中で眠る子供にすぎなかった」「私の罪はもしそれが罪と言い得るならば頗る明るい処からばかり写されていただろう、――同じ目で自分も見渡」すという立場に来ているのである。「則天去私」の大命題は段々崩芽を表わすかに見える。「明暗」に表われた「則天去私」についての考察はまたの機会にすることにした。
中川 貴先生 「雑感」
先日或授業において ”現在社会に極く普通にみられる利潤の源泉はどこにあるのか” ということで生徒に書かせて見た。所が、“そんなのは世界史とは関係ないじゃないか”、“利潤がなければ食って行けないじゃないか、それはあるのが当然で今更そんなことを” 、”安く買って高く売るから利潤が出るんであってわかり切ったことじゃないか” 、等々の反対(こうした疑問が無意味であり、従って無意味なことはやめろということだろう)が猛然と起った。この経験を通じて現在という条件の中において猶、学問とは何ととっつき難いものだろうと教えられた。学問は先ず “疑う” ということに出発点があることを私達は十四世紀以来の歴史の中から読みとる。けれども疑うということはこれ程難しい。
私達は兎角疑っちゃいけないものを疑ってかかる。即ち人間の善意さ等を、そして疑わなければその発展が止って了うものについては疑いえない。人間は元来天邪鬼だ等とおさまっても居れない。
そこで私は自分に帰る。教育とは?教師とは?…今更そんな事。
こうして時代は十三世紀以前へと逆転する。
生物部プランクトン班 大阪城濠のプランクトンの研究
私たちは一昨年の春当クラブに入部して初めてプランクトンを見てあまりの興味深さに感動しこの研究を思い着いた。七月の中頃八木沼先生の御紹介によりプランクトンの権威者大阪学大の水野先生に来ていただき、大阪城濠にゴムボートを浮べ、各種の水質調査や採集方法、研究のあり方、進め方等について指導を受けた。更に同年の九月中頃には横田先生から水中の酸素と有機物の定量方法をおそわり、十一月には各種の準備段階を経て実際の調査に乗り出した。以後時には薬品がきれたり、器具故障・破損・定期考査中等のためにぬけた事もあつたが、大体毎週土曜日測定・採集を続けた。班の人数は多い時には十名を上まわったが、残念な事に卒業や個人の事情でクラブを去って行かれ、少ない時は二人だけの時もあった。しかし昨年の夏休みまでには、それらの人々の協力もあったおかげで大体一年にわたる資料がたまった。先生のおすすめで昨年十一月十四日の大阪府高等学校生物教育研究会主催生物研究発表会に出場したところ幸にも第一位に入賞することが出来た。その後も今に至るまで調査は続けられ、次第に新入生諸君の手に移りつつあるが、資料はまだまだ不充分で今後の調査も有意義と信じている。後を継いで下さる新人生諸君に私達は大きく期待をよせている。なおこの研究の一部は昨年発行された九号の航跡に載せたが今回は今まで行なってきた研究の内容をまとめて発表する。
調査場所
採集地は主に大阪城内で京橋門を入った所の天守閣の大体西にあたる所(A)、そのつながっている濠の警察学校の向いでちょうど天守閣の東側にあたる所(B)、更に元国税局の門を入って天守閣の北西にあたる所(C)と、そのつらなりの濠の天守閣の北東になるあたり(D)の四地点で始めた。途中で時間短縮のために、(B)(D)を除いた。其他家の近所の淀川や遠足、修学旅行先、家から遊びに行った所、友達の家の近所等出来るだけ多くの所から採集し分類的資料に加えた。そして以下の三つを大体の研究目標とした。
一、大阪城のプランクトン相の調査、即ち大阪城の濠にはどんなプランクトンがどんな割合で生存するかと言う事を調べる。
二、プランクトンの消長の調査、即ち一年間又は何年もの間にプランクトン相がいかに変化して行くかを調べる。
三、二のプランクトン消長の原因探求、即ち天候、水温、日照時間、水中酸素、有機物のどれによって又は其の他の何によってプランクトンが増えたり減ったり更には消滅したりするのかを調べる。そして更に出来うればプランクトンの自然界に対する反作用を調べようと思う。
思いがけぬ誤りもあるかも知れないが今までに出た結果をここに発表する。
プランクトン相(略)
プランクトンの消長(略)
消長と環境の関係
1.水温との関係 出現最低温度が10℃のツノモは春~夏性の、出現最低水温が19℃のオオヒゲマワリは初夏に現われる夏性の代表的な種類である。また発見された最高水温が23℃のコシブトカメノコウワムシは秋から春に現われ夏性に対して冬性と呼ぶ事が出来る。水温はこの様に大変明白な生存範囲を示してくれる。即ち水温はこれらの種類に大きな影響を及ぼす環境要素である事がこのグラフによってだいたい証明されている。しかし他にはこのグラフに記入しても全く限界を示さぬ種類がある。これらの消長の原因は他にあると見るよりほかはない
2.水の酸素含有量との関係 水中の気体は酸素に限らず水温に左右されやすく多くの場合水温と比例して増減する。そのため消長の原因がこれによるものであるか、又そうでなくて水温によるものであるか断定する事は実験的調査を待たねばならない。即ち温度を自然状態のまま保ち含有する酸素を溶解度以下にしたり、溶解度以上にしたりして、始めのプランクトン相と比較すると言うような実験である。数種の実験方法を研究した結果、硝性没食子酸(ビロガロール)のアルカリ溶液中を通じて酸素を除いた空気を瓶にとった池の水と接触する事によって池水中の酸素を除く方法が最も適当な実験方法である事が分ったが本格的実験にまではまだ手掛けられなかった。従って酸素の方の結論は発表をひかえておく。
3.透明度との関係 先に述べた Closterium acutum は透明度と関連性をもっている。昨年と今年34年2月21日までの透明度の平均が105センチに対し、次の冬の34年12月5日から35年2月27日までの平均透明度が17センチ少ない88センチ弱となり、水面も一年間に150センチは下がったと思われる。Closterum acutumはこの変化によって絶滅したのではないかと思われる。もう一つの参考事項は35年1月4日に琵琶湖において一年前の(C)と同じ様に大変沢山のそれが発生していた。琵琶湖は気候条件において大差はないが、大きな湖だけに水もすんでいると言う事である。もしこのことが云えるなら次の予想が可能である。即ち「今後大阪城の(C)の水がふえ透明度が上がらぬ限り同濠に再度 Closterium acutum が繁殖する事はないであろう。
その他種類とこれらの環境との関係
先に述べた少しのものだけが第三課題の結論であって他の種類の消長の原因はほとんど分らない。しかし先にのべたものは、いずれも各々一種に対して一要素のけんとうであって今我々が研究しているグラフが何か発見してくれるかもしれない。そのグラフと言うのは、一面のグラフに数種の環境要素とプランクトン量を記入しようと言うものでこのグラフの完成には我々は大きな期待がもてると思う。後を継いで下さる新入生諸君にその完成に努力されんことをねがうものである。
プランクトンのプの字も知らなかった私たちが、ここまで研究出来たのもそれを指導下さった顧問の先生方を始め、研究に協力された部員のおかげである。筆をおくあたりここに改めて厚く御礼申上げる。
プランクトン班員名
三年 沢谷功・浅野征一郎
二年 佐伯一郎・松井寿三郎
一年 宮本武志・森沢道明・横田絢郎・源勝弘・市川喜久子・大江真千子・大西和代
(昭和三十四年度大阪府高等学校生物研究発表会 受賞作品)
9期生・3年1組 中野儀人 「犯罪と善性について」
近頃よく青少年の犯罪が激増したと云われています。そして、それと同時に映画や雑誌の不倫を強く、非難し改めるように要求していますが、私には、そんな人は果して現社会をよく見つめた上で云っているのか、不可解でなりません。実際、青少年である私でさえ一体全体、何が善性なのか、悪性なのか、又それをどんな風にして規定されるものか、わからないのです。その上、現代の社会の大人達は余りにも人間を人形のごとく見過ぎてやしないかとつくづく感じるのであります。人間というものは不思議なものです。我々は動物でないと云います。理性も良心も又深く熟考する力のある万物の霊長だと云って、我が得たらむ顔して偉張っている。確かに、我々人間は偉大な文化も、歴史を作り出して、他の動物とはあらゆる点に於いて、劣るところがないでしょう。けれども、よくよく考えてみますと人間ももともと動物です。機械ではないのです。唯賢い動物だと云うだけです。つまり人間はそのもの動物の範囲に於いて賢いだけなのです。だから野生さもあり、どうもうでもあり、又、動物同様の本能もあるのです。私達はどんな人であっても、空腹の時には、飲食店の前を通り過ぎる時、“あっ、あれ食べたいなあ“と思うのです。もっと極端な例を挙げますと、ヌード絵画を見せつけられた時には必然的に性欲をそそのかされるのです。もし、そうでないような人があるのでしたら彼は何と愚鈍な人間かそれとも、完全に麻痺された人間機械です。通常の常規を逸脱していない人ならば必ずそうなるのです。我々はそういうこと先ず認めることを前提として、現代のいわゆる犯罪を見なければ、到底結果としては人間でない人間を作るばかりではないだろうか。ところで、我々の若い者は、食欲を飲食店の前でそそられてからどうすべきか知らないのだ。というのは我々は、この人間機械社会には完全に慣れきれず、まだ真実の動物の中に居るものとした人間であり過ぎているからである。
昔、性善説とか性悪説などを唱えられていましたが、彼らはこの人間機械と動物人間との間を解きあかそうとしたのに違いない。ところが、残念なことに彼らは、無論現代もそうだが、どちらか一方を善、他方を悪とし厳として勧善懲悪をしたがためにそのような説はすべての人々から賞賛されはしなかったであろう。彼らは惜しいところまで行きながら結局、道徳とか何とかに陥ってしまったのだ。本来、人間は常に善と悪に悩まされては悲観しそして楽観した。善と悪どちらをも持たざるを得ないのである。私としては、善がどんなものか悪はどんなものかは、とにかく、人間は完全なる機械でもなく、又完全なる動物でない限り善と悪は持たなければならないし、又逆に両者の並立していないものは人間でないと思う。云はば人間の必要なそして十分な条件は、善悪両者を兼ねていることだと思う。だが決して善を勧めて悪をこらそうと云うのでない。現在必要なのは、そんなところではない。私はそんなことをする程の非人間的な者じゃない。私が両者が人間の必要十分条件だと云った限り、そうするならば前述と矛盾するので責められるべきである。
現在まで人間の歴史は千年を重ねている。そしてその長い年月の間にすこぶる高い文化を築いてしまった。それは、人間であるから、可能であったのだ。人間機械であっても動物人間であっても、それは不可能であったろう。ところが現在この高い文化の上に立った我々人間が最も馬鹿の骨頂が、一生懸命になって人間機械と動物人間とを分化させようとしている。それが結局、善と悪を分けようとすることになる。実に馬鹿だ。現代こそ、それらの融合の必要な時はないのだ。分けようとする結果、犯罪は絶えない、だから暖かさ即ち愛というものも消えてゆく我々人間が今まで汗を流して積み重ねた文化を保ち続けるためには、もっと人間的にならねばならない。云い換ればもっと、善と悪の融合を行って、善に強さを持たせ悪に白さを持たせねばならない。
3年1組 片岡健太郎 「宗教の本質」
宗教の本質は何であろうか。僕は時々からこの問題に興味を持っていたので、薄学の侏儒ながら一考を試みた。 六月三日付の朝日新聞紙上にグアム島のジャングルに十六年間隠れ住んでいた皆川さんという元日本兵とのインタービューの記事があり、その中に次のような皆川さんの言葉が書かれてあった。「十六年間、よくも生きてこられたものだ。バタバタと倒れる戦友。仲間は七人から三人へ、そして二人っきりに。さびしく恐ろしい生活、それを救ってくれたのは信仰だった。精神的にもいや実際に私を死地から守ってくれたのだ。幾度私は神に救われた事だろう。」「私達は出征の時にいただいたお守り、千人針をハダ身離さなかった。洞クツで拾った木彫のお地蔵さんも大切に持ち歩いた。さまよい歩くうち、私はいたる所で戦友の落としたお守りを拾って身に付けた。寺、神社、合わせると二十種類程有ったがそんな事は問題じゃなかった。伊藤君とはこの問題で言い争う事もあった。しかし私は信じた。信仰がなかったら恐らく精神的にも参って、島の生活はとっくに終りを告げていたかもしれない。」
そして信仰を持ったために土民の銃殺を免れたとか、隠れ家を見つけられたが偶然外にいたので助かったとかの具体的な例が添えられてあった。
私はこの記事を読んだ時、これが宗教の根本なのではないかと思った。人間社会にあっては人間は精神的に肉体的に頼るべきものは先生、肉親、書物等あらゆるものが揃っている。ところが人跡未踏のジャングルの中では、何に頼るものがあろうか、あるのは人間社会、肉親や友達と遠く離れているという寂しさ、土民への恐怖、食糧の欠乏、あらゆる物が彼をこの世から消し去ってしまおうと襲いかかる。そんな時、彼が何か神秘的で絶対的なもの、具体的には現われないが彼が絶対に自分を救ってくれると確信できる、科学を超越した、彼の心の中で大きな力を持っているもの――神、仏に救いを求め、それらを信仰するのは当然の事だろう。そしてそれを実際に行った結果がおまもりを集めて大切にしたとか、仏の像を肌身離さず持っていたとかの行動なのだ。このような信仰は人間の最も基本的な宗教の信仰形態だと思う。そしてさまざまな宗教が現存しているのはこの基本型に環境の差、考えの差が加わったに過ぎないと言える。宗教の本質を摑むには、出来上った宗教の教義を調べるだけではだめで、宗教は人間によって生みだされたので、人間そのものの環境を研究せねばならないのである。
宗教とは人間の環境が全く頼れぬもので構成されている時、他に求めるものがそれなのであるが、今我々の住んでいる社会にはどんな宗教を求める原因になる頼れぬ所があるのだろうか。若い我々にとっていつも関心を払っていることは、毎日の授業であり、遠い未来であり、日常生活の現実的な事柄ばかりであるこのような我々の生活にはジャングルの生活時に求めるようなものはないように思える。しかし、いつも自分以外のものに気をとられている状態から脱して自己に立ち帰り、自己の事を深く考えると、必らずや、自身がこの世の中に生きているとはどういう事か、何故何のために生きているのか、等の深い問題に到着するであろう。この場合、世間一般のとおり一ぺんの説明ではとても解決できぬ問題であろう。いかに科学によってこれを説明しようとしても不可能であろう。この問題を解決し、その人に安心感を与えるのは他でもない、宗教である。
3年1組 雪本 (博) 「マス=コミュニケーションのあり方」
石器使用、摩擦による火熱使用時代以来、いや十年前からこの世界のあらゆる発展、人工衛星が、ICBMが飛ぶ現在は科学の時代と呼ばれている様に本当にめざましい進歩に進歩が重ねられている。現在の科学の発達は日常生活を合理的かつ幸福、富、等を与えあの原始時代と比較してみると格段の進歩の相違がうかがわれるであろう。科学の発達と共に文化面も社会面も自然界の面もあらゆる面が進歩して来ている。だが反面これらの科学の発達は相互間の友情、親愛感を利己的方面に流入していく事が見られる。たとえば人民民主主義国家群と自由主義国家群との相対立としてこの二陣営間に“冷たい戦争”と弥せられるべき物が起ってきている。この事はさておき、この科学発達による社会の変化と共に発展してきた現代の文化は世界全体の相互的なものである。この現代の文化は教育というべき触媒物の進歩がなければ発展しなかったといっても過言でない。
この教育体の中でますます科学の時代にともない隆盛をきわめ広大な存在範囲を占めているのがマス=コミュニケーションというものである。マス=コミュニケーションとは社会の現象をとらえて批判を加え反省を促す文明の利器であり社会悪を断ち切るつなぎであり大規模な組織で大ぜいの人間に伝達を行い娯楽をも与え新聞、ラジオ、映画、テレビなどで人間の視覚、聴覚に訴える手段、大衆通報機関である。
社会を導くべきマス=コミュニケーションは真実、真理を追求明確にしその真実を多数の人に速く正確に伝達するものでなければならない。ただ単なる批判も加えない事実の記録的写実的、独自的判断でなく国民大衆に考えることのできるべき道を開かせるものでなければならない。娯楽面でも健全な娯楽を与える事であろう。所で今考えてみたいのは現代において以上の様なマス=コミュニケーションはこうでありたいという様な事がはたして忠実に実施されているかどうかである。
もちろん行われているべきであり行われていると考えてよいかもしれないが、一方、マス=コミュニケーションは文明の利器であり社会悪を断ち切るつなぎであるがそれ自身がうわついてしまって一億白痴化などという批判を逆に受ける場合は往々にしてある。特に娯楽面ではよく現われているであろう。青少年犯罪が増えるなどはマス=コミュニケーションの影響のみだとは限定されないがマス=コミュニケーションの影響のみだとは限定されないがマス=コミュニケーションの影響が多大に含まれている事は確かな事である。又ある新聞などではいわゆる一種の一般社会、全国民の身辺に何らの影響のない駄作記事をでかでかと取り上げて重要問題であるといわれる記事などに一筆も手をつけていないという事がある。
一方マス=コミュニケーションは営利主義に流入してマス=コミュニケーションのあり方と言うべきものをおろそかにし、金にさえなればよい「発行せよ、発行せよどんな内容でもよい」と言う様な事が無きにしもあらずである。又マス=コミュニケーションが広範囲の意味の宣伝が行われる様になると社会の最大多数の民衆の意見、即ち世論も危機な面に陥るそして一方向に傾むいて行くという事が予測される。
この様な実情である今日のマス=コミュニケーションをこの科学の時代の中に生存している我々はよりよき幸福な社会が築かれていくようマス=コミュニケーションというものをも注視してほしいものである。
3年2組 天本登志子 「孤独と人間嫌い」
いったい人間嫌いになるという事はどんな事を言うのであろうか。よく耳にすることであるが、人間嫌いになる場合、それはあらゆる方面からなる。人生は快楽ばかりでは終らない。人生ははてしない旅である。それが、はかない旅であっても我々はかない者にとってはこれ以上最大の旅はない。その中に我々は、まして若者は孤独になりがちである。
「人間嫌い」との言葉も孤独から出発する。孤独とは一言に言って真に偉大なものであり、すばらしいものである。なぜならば真の自己を知るからである。孤独を求めたがるのは、醜い空虚な演技からぬけたい為であり、厚い仮面をはずしたいからである。人間嫌いは自己を除いての場合と自己を含めての場合とがある。前者は自己のみが純粋であると考える。自己のみが善だと考える。自己のみが正だと考える。他人がすべてきたなく思え、偽善に思え、あわれに思える。そして最後にそう自己のみで満足していることに増々いやになり、今度は自己を含めて人間そのものにいや気をさし、人の話を聞くのにも、疲労感を味うことになり、理由もなく眼を反対の方へ向けてしまう。人間の会話がとても幼稚なものに感じられ、馬鹿らしい会話に思えてくる。人間は、このような物であったのかとそこではじめて悲観し、人間に対してさみしがるのである。
人間は、もともとそういうものであったのにもかかわらず、なお今でもそれと反対のものを我々若者は求めている。「おはよう」という会話に空しさを感じて、「さよなら」という会話になにかしらあわれみの様なものを感ぜずにはいられないものである。いずれにしても人間そのものが行うことに、はかなさ、さみしさを感じる。一人の幼い子が道ばたで無邪気に砂遊びをしているのを見て、喜ばしいよりも、さみしさを感じてくるものだ。これが孤独に通ずる。人間嫌いなのは、人間の悪のかたまりが、偽善のかたまりが、見栄のかたまりが、ひしひしと渦を巻きながら、胸のおく底までしみ込んでくるのである。
人間嫌いになる事が、果して悪い方向へ進むだろうか。むしろ良い方向へ進むだろう。人間がある時非常に耐えられぬ程、孤独になり、人間嫌いになる。(一生そうだとは決して言えない。もし一生人間嫌いになってしまえば生きている必要はない。その様な人は、自殺するであろう。あまりにその人が純粋であるがゆえに。)でも人間はその孤独からいつかはぬけ出るはずだ。そのぬけ出た時、再び自己を外から見てみよう。孤独を知らない人、人間嫌いになったことのない人と比べて、どれだけ人間性が違うか。自己を知った真の自分程、幸福なものはあり得ない。だからといって無理に孤独になる必要はない。ただ孤独になる人とならない人とでは、孤独になる人の方がより幸福だと言うことに他ならないのである。孤独からぬけ出た時の再出発する目を見よ。未来に輝いているはずだ。それはそのはず自己を良く知ることが出来たから、その前までのつまらない気まぐれな考え方、行動において深く省みたからである。だから以前の自己と現在の自己とでは表面的にはわからなくても内面的には、どれほど進歩した事であろうか。孤独は、自己のみが目をとじるものであり、又自己のみを目ざす唯一のものである。幸福に近づく一歩を歩いたことになる。
我々は孤独を知った人を親しき友とするが良かろう。なぜならば彼等の会話には真実性が存在し信頼というものがはじめて生じるものなのだから。聞いていても決して空しい会話ではない。人間というものは、気ままで、勝手なものであるから、孤独になりたいと一心に願う時もあり、人間嫌いになる時もあれば、それと反対に万物が美そのものに見えることもある。人間に感謝したい時も少なくないのである。もし我々が孤独になったら、そして人間嫌いになったら、その時、より良く自己を省みて、明日への生活により良いものを持っていきたいものである。孤独とは、単に人間から逃げるばかりではない。自己そのものが主人公であり、すべてに自由でもあり、自分にとっては価値のある、かけがえのない時でもある。孤独を大切にしよう。自己を愛するならば孤独をも愛すべきである。我々は自己を知りすぎる程知らなければならないのである。孤独があるからこそ、そして人間嫌いになる時があるからこそ、人間の純粋さ(わずかなものかもしれないが)は永遠に消え去らないのである。最初の人間は純粋であったのだ。我々はそれにもどるまではいかなくとも、もっと純粋な気持になろうと努力すべきである。それには何が重要であろうか。自己の「自己」を知ることである。それは孤独を知る事である。孤独を知ると共に自然をもっと知る必要がある。いや自然にもっと親しむべきである。我々が関心を持つものは、ヒューマニズムばかりではない。自然を知ることである。月に親しむべきだし、夜空の星に親しむべきである。すばらしい 孤独は、自己が創り出すものである。
我々の中で孤独を恐れる人が少なくない。孤独のさみしさに恐れるのであろうか。孤独というそのものを自確し覚悟しておれば、なんのさみしさも生じなないことは確かであろう。それこそ賢い生き方に違いない。孤独になるということは、単に一人になるだけではない。我々をより良く純粋なものにしてくれるのが孤独であり、人間嫌いになることである。我々誰しもが純粋なものになりたいと願うのは当然の事であろう。それには、自他をはっきり知り尽して、よくよく人生をながめることである。若者がいう孤独とは永久的なものでなくて一時的なものである。永久的に孤独になるのは、とても苦しく、いや苦しさでなくて(肉体的苦痛でなく)この世のけがらわしさ、くよくよする動物の姿等が、その孤独を、やむをえず奪い取ってしまう有様である。だから死ぬ時一生を孤独で暮したいという人がもしいたとしたらどんなものであったかをたずねてみたいものである。詩人は、一生孤独を知らなければならない。知らなければならないというのではなく、それを知ってこそ、人生の喜びを感じ、詩への熱望が生まれてくるのである。詩人は聖人だ。我々は詩人にならないまでも、詩人の感覚を少しでも認める方向へと進まなければならないのだ。
人間はもろいものだ。わずかな薬品で最後を遂げる「物」である。だが人間は、「物」ではない。なぜなら自己を知ることが出来、他を認めることが出来るではないか。人間の孤独そのものが幸福なものである。ただここで注意しなくてはならないことは、自分の内に入っていくことは良いことであるが、あまりに内に、自己の内にとじこもることは危険である。孤独になり真の純粋の「自己」を知って、その中で堂々と生活すればいいのだ。自分の道は、自分で見い出すものである。ある人間は孤独になることに優越感をいだく人もいるであろう。だが真に孤独になることはそんなものもどこにか、かくれてしまう。我々は孤独の中で、精一ぱいに努力し、惜しみなく学ぶことである。その日の為に真剣に生きていかなければならない。
3年2組 木下睦美 「愛国心について」
愛国心とは、案外難かしい問題である。愛国心は人間の歴史とともに古く、また歴史とともにいろいろ変化してきている。そして“歴史”と“自然”は人間がもっている一番すぐれた先生であると思う。「愛国心とは、自分の国家を愛し、その発展を願い、これに奉仕しようとする態度である」。しかしこれは形式的定義にすぎない。この言葉は確かに我々の心の急所にふれる。そして如何にも後味が悪い。ハッとするけれども、その後に、何か割り切れぬもの、宙ぶらりなもの、カスが残る。どんよりとしたものが心の底に澱んでいる。この後味が悪い、カスのようなものが残るという本当の内容は? ある人は、日本という国に絶望し、愛国心の内容が明らかでない事に悩んでいるだろう。又ある人は、過去に於ける愛国心に対して不愉快な記憶を持ち、愛国心等という時代は過ぎ去ったと思いながらも新しい日本の事を考えているだろう。
このように国民的心理を考えると、現在の日本人の大部分の気持をつかむ事が出来るであろう。我々は、自分の国に対して自然的な愛情を抱いている。この愛情が如何に根強いものであるかは、遠く故郷を離れた時にはっきりと理解されるであろう。愛国心の芽ばえは自分がその中で生れた仲間に親しみを感じ、仲間でない人間を敵のようにおそれる。
これは、何百年か昔、この地球に始めて姿を表わした人間の先祖達ももっていたにちがいない。生れ、育った故郷は森や林、ながれる小川、道をはさんでつづく家の軒と軒、そして 友人、家族、家屋、道具等たまらなく懐しい仲間に親しみ、敵をおそれ、ふるさとを愛する心。ここに愛国心の芽ばえはあるのではないだろうか? 我々がそのように、愛情、親しみを感じるのは、壮麗なもの、偉大なもの、特別なものではなく、むしろ、つまらぬ日常的なものであるのが普通である。
シャトーブリアン(Francois Rene Chateaubriand, 1768―1848)は「毎晩吠え立てる犬」「庭の樹の向うに見える教会の塔」「忠実な下男の顔」などを祖国への愛情の内容として指摘している。
レオンハルト・フランク(Leonhard Frank)も又「祖国とは吾々が、子供の時に夕方になると遊び廻っていた小路のことであり、石油ランプが静かに照らしている食卓のことであり、植民地製品を売っている隣家の飾窓のことである。祖国とは、吾々がその実の熟するのを待っていた庭の胡桃の樹の事であり、谷川の事であり、谷川の湾曲部の事である。」
外国に住むイギリス人が懐しく思うのは、あの陰うつな霧であり、又祖国の事を考えるフランス人の胸に先ず現われるのは、故郷のだんろの火である。セント・ヘレナに流されたナポレオンの夢に現われたのは、パリの華麗な生活ではなく、淋しいコルシカの風物であった。故郷を慕うことが烈しいという点でスイス人は古来有名である。「これらから離れていると、人間は片輪であるような感じがする。それと共にいない限り、人間はどうしても落着く事が出来ない。安心する事が出来ない。」と清水幾太郎氏がのべている。
時代は下り、愛国心の歴史をたどろう。
都市国家(ポリス)であるスパルタのある母親は、戦争にいく子供に、盾をわたしながらいった。「この盾を持って帰れ、でなければこの盾にのって帰れ。」 勝利でなければ死をという意味である。しかし戦う相手は同じギリシャ人である。
またギリシャ人達は、他の民族を「バルロイ」すなわち「きたない人間」という名で呼び、自分達を「ヘレネス」とよび、「すぐれた宗教」「美くしい言葉をもつ民族」と考えていたらしい。しかしこの愛国心と今の愛国心は大部ちがったものである。
中世の世界をおさめていた法王は、民族をこえてヨーロッパの全体に力をもっていた。どの国民も絶対の力を持つ国王のもとで、愛国心はもり上っていった。
そして十九世紀の中ばすぎると、愛国心はだらくしてきた。政府が国民の間に愛国心を高めようとした腕ずくの愛国心であった。
日本でも明治維新に入り天皇に対する忠義と結びついていた。このように国王のための愛国心、力ずくの愛国心は、もはや時代おくれである。しかし不必要なものでないと思う。自分の国を美くしくもっと明るいものにしようとする愛国心はまちがいでない。
人間の歴史は小さなひとかたまりの人々の共同生活から何千万という人々の統一国家にまで発達した。やがて愛国心は世界の人々をつつむ人類愛まで生長するだろう。
最後に愛国心は民主主義を基礎として成立しているという。近代の愛国心にとってもっとも重要な事は民主主義との関係である。
3年2組 松原秀文 「幸福について」
私たちは幸福について語ったり、考えたりすることを何か後めたいことのように感じてこれを恥ずかしく思ったりする。私たちは自分自身の幸福について云々することを、ほこりとしなければならない。
いったい幸福とは何であろうか。それはまず私たちの生活の上に考えられるものでなければならない。生をはなれて幸福はないのである。しかしながら、ただ生きているというだけでは私たちは無論まだ幸福とはいわれない。幸福な生活とは「生きていていいな」と思い「人生は美しい」と感じさせられる生活なのである。善美なるもの、それが私たちを幸福にするのである。 しかしまた幸福と共に不幸も始まるといわなければならない。ぜなら、”よりよい生活、にくらべれば、どんな生活も不幸の影を帯びて来るからである。ほかに何の不足がなくても何かひとつ足りないものがあれば、それだけでも不幸は絶体絶命と感じられる。賞される不幸もあれば、あわれな幸福もある。つまり幸福は私たちの生活が向上し、善美な何ものかがつけ加えられる、その一歩一歩のところに見出されるという事が出来るであろう。
それでは人間は幸福になることが出来ないのであろうか。善美の極をつくし絶対の完成に達するという意味では人間は神のようになるのでなければ幸福に止まることは出来ないであろう。しかし人間としての幸福は、いかにあわれなものと見えるにしても、なお私たちに許されている。それは私たちの能力にあわせて私たちの欲望を制限することから生れて来るところの生活の平等であり、均衡である。不幸は不足の感じから生れると思う。 何の不足もない生活が、すなわちまた幸福な生活なのだと思われる。極端に言えば、何も初めから求めることをしなければ、何もいらないのであるから何の不足も感じられず、私たちは不幸を知らないことになる。しかし何も求めずに単なる生存に甘んずるということは、不幸を知らないことであると共に、また幸福をも知らないことになるのではないかと疑いたくなる。どんな文化をも否定し、生活の向上を断念することだけが果して幸福への途であるかどうかも同様に疑いたくなる。 動物の幸福なるものは私たちの想像のうちにだけ存在するのである。単なる生存には幸も不幸もない。幸福は単なる生存以上のよりよい生活のうちにあるのであり、そこには不幸も始まるかも知れない。がまた幸福も見出されるのである。私たちは不幸を恐れて幸福をあきらめることは出来ない。 では私たち人間の幸福は、どのようなものであろうか。それは私たちに生活の向上を許し文化の発展を助けるものであると思う。人間の生活はいつも単なる生存以上に出るのであって、そのいたるところに幸福を見出すことが出来るからである。乞食生活のうちにも幸福を見出すというのは、たしかにかしこいことではあるが、乞食生活に甘んじているということは決して良いことではない。たとえ百の不幸を招くにしても、あくまで、よりよい生活〟を目ざして幸福への意志を持ち続けることが望ましいとも考えられる。しかしながら幸福はよりよき生活のうちにあるとしても私たちの生活がいつも向上の途にあるとは限らない。 私たちは人間としての幸福をのぞむならば現在の不幸を、さけてはならない。私たちは不幸を不幸として受け取り、いつもよりよき生活、 を用意しなければならない。私たちは幸福を欲するけれども、そのために不幸を恐れてはならないであろう。幸福は万人の願うところである。
3年2組 野原 忠 「ヒューマニズムについて」
ヒューマニズムの問題は人間形成である故にそれは単なる解釈の立場でなくて、行為の立場に立つのでなければならぬ。人間は行為することによってのみ真に自己を形成することが出来る。しかも人間が自己を形成し得るのは常に社会においてである。けれども社会的になるということは、ヒューマニストにとって自己を失うことではない。
ヒューマニズムがともすれば、非行動的になるということは注意を要する。もとよりヒューマニズムは単なる闘争主義でなく、平和や調和を愛するけれどもヒューマニストにとって、如何なる行動もつねに内面的な人格的な意味をもっている。それには良心と正義の問題がある。ところで行為の立場は単なる内在論であり得ない。この点において従来のヒューマニズムの哲学には重大な制限があり、それが行動的でなく観想的であったということもこの点に関係しているであろう。自己の外にしかも単に自己の意識の外にというのみでなく、むしろ自己の身体の外に超越的なもの、独立的なるものを認めるのでなければ、行為というものは考えられない。
しかるにこのように外において超越があるのは、自己の内において超越していたためである。内における超越がなければ、行為というものは考えられない。行為は二重の超越において可能になるのである。
3年2組 村林 正策 「ヒューマニズムについて」
ヒューマニズムは人間の解放を求めるものであるが、解放をもとめるのは少数者の特権階級に対する大衆であるのが常である。ルネツサンスのヒューマニズムは市民階級の握頭と結びついている。従ってヒューマニズムはその本来の精神に於いて民衆の側に立つのではなければならぬ。ゴーリキー等のプロレタリア・ヒューマニズムは単なる人間解放の要求でなく、人間再生の要求であり、この要求は一の内面的な主体的な問題である。ヒューマニズムが単なる政治主義でありえないのもその為である。もとより人間は孤立して存在するものではなく、人間は環境からつくられるのである。或は人間は社会から生れるのである。従って人間が新たに生れるためには、社会が新たになければならぬ。しかるに人間は単に社会から規定されるのでなく、独立なものとして逆に社会に働きかけ、これを変化する。もしも人間が環境の産物にすぎないならば、ヒューマニズムのいうような人間の品位は考えられないであろう。人間は社会から作られると共に、逆に社会を作る。かようにして人間が新たに生まれる為には、社会に働きかけて、これを変化し、この新たになった社会から人間は新たに生れるのでなければならぬ。ヒューマニズムは人間の革新と社会の革新とを統一において把握することが必要である。ヒューマニズムというのは人間性と人間性想像とにかかわる一定の思想である。それは人間の尊さを考え人間の品位を重んじる、しかしこれだけではなく、歴史的意味におけるヒューマニズムがヒューマニズムとして現われるのは常に一定の歴史的時代もしくは一定の歴史的情況においてである。
もし人間の創作したものが人間に対立し、やがて人間を束縛し抑圧するに至るということは歴史の根本法則である。人間がつくるものはもとの人間の発展の為に作られるのであるがそれがやがて人にとって桎梏に転化するに至る。この時人間の解放が要求されるのであってヒューマニズムはそのような時代における人間の態度である。ルネッサンスの時代のヒューマニズムは封建的なものからの人間の解放であったし、ドイツのヒューマニズムも新興市民階級の政治意識と結びついたシュトゥルム・ウント・ドゥラングの運動から出たものである。現在のヒューマニズムは現代が社会の一つの転形期であるという事情に相応するのであろう。
ヒューマニズムは解放の要求であることから、解放さるべき人間性は「自」「然」と考えられ人間主義であるヒューマニズムにとって根本的概念が却って「自然」であるということも生じ、かくして単なる人間主義はヒューマニズムでないというようなことも生じる。我々はヒューマニズムが絶えず自然の思想と結び附いて現われたことに注意しなければならぬ。自然についての新しい見方が新しいヒューマニズムの基礎になるとさえいえるであろう。
3年3組 平尾泰朗 「信じるということ」
信じられない。信じることが現代人にとって、いかに困難であるかは、あなたもよく知っています。このような一節を見、聞きした人もあるでしょう。本当にこの現代に生きる人間どもの渦流の中にあって、信じるということは実に困難であり、恐怖の冒険にも似た感じさえ受ける。空気を吐くように嘘をつき、空気を吸いこむように偽りを吸うこの世の中にあって、魂の純粋な、体験に乏しい人々は、偽られていることなど夢にも気づかず、何の心もなく信じるということをやってしまうのである。そして、血みどろの傷を心に受けて、はじめて判断なく信じこむことの間違いに気づくのである。魂の純粋を忘却してしまったのである。自己を欺かないように、不用意に人を傷つけないように、努力するのはむろんのこと、信じるに足るものかどうかを、深い心の眼で、磨きあげられたウィンドーウを透して見分けることが必要条件となってくるのだ。しかし、信じるに足るものに対しては、信じるという言葉すら不必要なほどの絶対の信頼をもてる人間でありたいということは、あなたも思っているのです。
あなたが、こうなった時、あなたは、信じることができたのです。愛してしまったのです。愛されたのです。信じられたのです。そうです。これをある男が、信愛と呼びました。遠い昔のヒューマニズムの誕生時代のことだった。
3年3組 入江脩二 「民主政治について」
約二ヵ月前に韓国が革命を起したことは、まだ記憶に新しいことと思う。この革命の最も主な原因は、李承晩政府の不正選挙が大きな原因ではないかと思われる。
この革命の発端は、三月十五日、大統領選挙抗議デモで、高校生と市民がはっきり反政府の火の手をあげた。これが第一次馬山事件である。
しかし、それ以前に起された、高校生だけによる反政府デモを、その発火点と考えてよいのではなかろうか。何故なら、選挙当日の午後に起された馬山事件は、主に、選挙の不正に対する怒りによるものであって、その他の圧制に対する批議は一応別扱いにされていた。 以前の事件とは、二月二十八日、大邱で起った高校生デモである。この日、学生は、長年の李承晩政府の圧制に憤慨して、「学園の自由」と「学生の人権確立」をスローガンに掲げ、憤然と立ち上がったが、警察の弾圧が激烈であったので、高校生側は多数犠牲者を出して、鎮圧された。しかし、この事件で韓国の各地方で次第に高校生の圧制批議デモが起った。
しかし李承晩政府の教育自身は、別に悪くなく、教育形式は全体主義のものでりっぱな学校がたてられたり、設備も日本の学校にくらべて、いっこう見おとりをしない。むしろ新しいだけに、中、高校生のレベルでは、種々の点でまさっている場合すらあるらしい。だが李承晩政府は青年の教育には、情操教育に重点をおくより「愛国心を養うこと」と「科学教育に重点をおいた教育を行うこと」と「健康な体をつくること」の三つであった。これは我国のような学校と違い、国民学校(我国の小学校に当る)から一貫した基本方針になっていたが、北朝鮮を初めとする共産勢力に対抗する李承晩政府にとっては必然的な教育内容であった。このような全体主義的教育の成果が、逆に現われてかえって李承晩政府の独裁的な、暴政を倒す原動力となったのはひどい矛盾した話である。このように韓国の高校生は自己の意見をしっかりもって、団結しているのは、我国の高校生としては、まったくうらやましい次第である。
今我国でも新安保の事で、えらくもめているが、これも岸首相の独裁?的政治の為めでもある。岸首相自身民主主義政治をとなえ、さらに、三悪追放までいうているのにもかかわらず、岸自身、民主政治を無視しているのは、万人の認めるところである。
新安保の内容はともかく、また僕達は選挙権を持たないから、新安保について、意見をのべる立場でないが、近い将来選挙権も得、立派に一人前の人間になるのであるから、ある程度自己の意見を持ってもよいのではなかろうか。
3年3組 安藤利子 「人間として」
人間って何だろう? 正体は全く不明だ。何かの物の書には、神が外界の全てのモノを創造して後、それらを神に代って支配するモノとして初めての人間アダムとイブを造られたとか…それも事実か否かは誰も断言する事は出来ない。まあこの様な事は後として、現在、地球上で一番高等な動物は人間である事は間違いではない。いや、ひょっとすると我々の目に止らない所に、人間より高等なモノが地球上に存在するかもしれない。でもまあ、それは何物であるか、又、本当に存在するかどうかは現在のところわかつていないのだからほっておこう。ずっとずっと昔から現代に到る迄人間は、人間以外の生物に征服されてはいない。人間は非征服者ではなく、征服者となる何かを持っているに違いない。それは、「モノを考えるという事だ。よく犬とか、猿とか、鳥とかが計算なんかをするというのを聞いたり観たりするが、それらは皆条件反射によってなされるものだ。彼等が勝手に頭脳で考えて計算するのではない。しかし人間はそれらとは全く異る。即ち、「考える頭」を持つ。それでいろいろな事を考え創造し、行動してきた。又、これからもそうであろう。だけど何故個人個人の考え方が違っているのだろう。全て同じ考え方であったら進歩も発展もないというのだろうか。又、かってはみんな同じであったのが、突然変異か何かで、ヒョコンとみんなと少し違った偉い考え方をする者と、少し愚かな考え方をする者とが出来て、長い期間の間で現在の様になったのだろうか。それとも環境が人間の考え方を変化さしたのか、いや、神が最初から各々異った考え方をする者をお造りになったのであろうか。我々は地上に生れて来てからこの方、誰から自分の意見が対立したり、食い違ったりしなかった者はいるだろうか、いや絶対にいる筈はない。皆んな各々いろいろな形で対立した経験を持っている。しかし、自分の意見を相手にも押しつける事は許されない。だが相手が自分の意見を良いとして受け入れてくれるならばそれで結構。この受け入れがなくて、押つけ様とするのと、拒否して自己の意見を出そうとすると、そこに争いが生じる。この争いによって過去にどれ程多くの人々が傷つき死にはてていったことか。美しい争いはなく、あるのはみにくい争いのみだ。いつの世にも争いはあった。各々時代により方法、原因、損害等も異っていた。争いをしている時の人間の心には善はなく、悪のみだ。どの様な手段を取っても勝とうとしたその恐しい心はどの時代に於いても一であたる。その恐しい心を人間は一面持っている。だけど美しい面も全ての人は持っているのに何故胸の奥深くしまって出さないだろう。美しい心に打たれない人はいないだろう。人が人を愛し、人が人に愛される事はとても美しいことだ。純粋な気持で生きる事は非常に大切である。人間の徳を発揮してこそ美しき園は営まれる。人間っておかしなモノだ。美しく生きようと思えば生きれるし、汚なく生きようと思えばこれも可能である。でも、美しく生きる人間の方が幸せだろう。少しはましな人間で生涯を終ろう。
3年3組 滝口勝久 「ヒューマニズムについて」
私達は大いなる希望をもって、人間の善意が善意としてとおる世の中をつくっていきたいと思う。この行為の原動力となる純粋さと正義感とは別のいいかたではヒューマニズムという名で呼んでもよいだろう。このヒューマニズムの発現の形式にはいろいろの種類があるが、いま具体的に、私達が大きな責任をおわされているわが日本社会での発現として「新安保反対」のやかましい今日で祖国愛の問題にふれてみたいと思う。
「祖国愛」というものは、太平洋戦争中の忠君愛国的なものをさすのでは決してない。それはヒューマニズムの基調のうえにたった本当の祖国愛ではなかったからである。ヒューマニズムはあくまでも自己を愛することが同時に他を愛することでなければならないのに、かってはエゴイズムに立脚したいつわりの祖国愛が横行したため戦争につぐ戦争がおこらざるをえなかった。
それではヒューマニズムに立脚しない祖国愛はなぜ本当の祖国愛ではないのか、私達は普通、祖国という場合、地図の上にえがかれた本州とその周囲の三つの島とを頭に想像していうことが多い。だがその様な「祖国」は単純な「地理的祖国」とでもいうべきものにすぎない。軍国主義が猛威をふるった時代のわが祖国の概念は、主にこうした地図上の赤い境界線に表現された、あやまれる「祖国」であった。だから軍国主義者達にとっては、祖国愛の内容は、ひたすらこの境界線を外側に拡張すること以外にはなかった。そんな「祖国愛」では、それが発揮されるごとにどこかの民族や国家がギセイにならねばならぬことは当然であった。ヒューマニズムの問題は人間形成である故にそれは単なる解釈の立場でなくて、行為の立場に立つのでなければならぬ。人間は行為することによってのみ真に自己を形成することが出来る。しかも人間が自己を形成し得るのは常に社会においてである。けれども社会的になるということは、ヒューマニストにとって自己を失うことではない。
これは本当の祖国及び、祖国愛ではない。では本当の祖国、及び祖国愛とは何か。それは「地理的祖国」すなわちわれらのこの美しい国土に、わが民族の優れた歴史と伝統その文化と精神、そして自由へのやむなき民族の希望が統合されたものである。この祖国に対する愛が、ヒューマニズムに立脚しているかぎり、われわれは当然、他の国土や民族をおかしたり圧迫しないかわり、同時に内外をとわず、この祖国をおかし、民族の自由をうばわんとするものとは、どこまでもたたかわざるをえない。
いま東京を中心として国内に新安保問題をめぐるみにくい国民同士の争いがくりかえされているとき、私達は、ヒューマニズムについてそれを祖国愛という立場からしみじみと考えさせられる。
3年4組 亀田寿子 「涙の英知」
涙というものはただ悲しみの現われというばかりでなく、美に触れたときにも、非常な喜びを態じた瞬間にも、急に心労から解放されたときにも、わき出てくるものである。こんな場合には、いかにも不合理で、ふさわしくないような感じを受ける。しかしこの思いもしなかった行動も、人間の心の最も強力で奥深くひそんだ欲求と秘密とから出発しているものなのだ、と現代心理学は教えるが、これは非常に意義深いことである。だから、この不可解な涙こそ自己啓示を受け、知恵を得、一層深い幸福を得る手がかりとなり得るのだ。
ある日の午後、中風のおじいさんが車付き椅子に座っていたのだが、与えられたアイスクリームを床に落してしまった。楽しみにしていた微笑は消えて、大粒の涙がハラハラと頬を伝って流れた。付添いの女はいっときこれを見つめていたが、やがて小部屋に駆け込むと赤ん坊のように声をあげて泣いた。そのわけを聞くと、その女の人は、「だってあの方あんなに年をとっていて、あんまり哀れに見えるんですもの・・、判るでしょう・・。」だがもしこの人が自分の気持を表現する言葉を見つけることが出来たならば、この涙には、もっと意味が加わったのだと思う。人間ははかないもの、死はいつもそこらをうろつきまわっている。人は互いに同情し合おうではありませんか、と言ったであろう。
ところが、私たちは多くの場合、同情への衝動を恐れ、無感動なふりをして、いわゆる「感傷」を笑っている。涙がわれ知らずほとばしり出るとき、やっと人間同士の間にあまねく同情というものが必要だという事をさとるのです。
思いもよらぬときに不思議に涙が湧き出る場合、その涙の陰には、こうした洞察が私たちを待ち伏せしているのだ。中世の大伽藍を訪れて目をうるませ、何とも言い現わせないような感情にむせんだ旅人が数知れない。何故の涙か? 壮麗で精緻を極めた伽籃を見た場合、なぜ単純に歎賞と喜びの微笑を漏らさないのか? これに対する答は、察するところ、ずっと昔この世にいた無名の人たちの努力と希望と功業とが瞬間的に示されたということの中にある。参観者は伽藍の正面の驚くほど精巧な彫刻をながめ、これまた細かい彫刻をほどこされてそそり立つ控壁を見上げては、幾百万回もくり返してノミと金ズチがたんねんに打ち下ろされた事を思い、それを使ってたこが出来た痛い手、疲れた筋肉と疲れた脊骨、工人や設計者の満足した誇らしげな顔などを思い浮べるのである。
この同情の涙と同様に、喜びの涙も私達の隠れた面について教えてくれるところが多い。この涙はまざり気のない純粋な幸福からくるものだろうか、いや、ある本に書かれていた精神病学者は、人は純粋な喜びで泣くことはないという結論を出した。そんな涙にはいつも悲しみが隠されているというのである。結婚式で、ただ純粋に幸福にひたりきっている花嫁は泣かない。母親は、これも嬉しいのではあるが、その瞬間までわが子であった者に訪れてこないとも限らない悲しみのために、そしておそらくは母親は人生における自分の役割の一部を失ったと感じるために、泣くのである。純粋に美しいものに接して涙を流す人もある。突然目の前に水仙が一面に咲き乱れている所にくると、思わず涙をパラパラと落し、高くそびえる山脈、山ふところの青い湖を初めて見、また、噴火口から中を見た時の驚き、モーツアルトのソナタの完璧な美に初めて接して泣いた人等・・
涙を流して泣く生理を研究すると、完全に緊張した状態、または完全にくつろいでいる状態ではめったにそういう事にならないことがわかる。そうなるのは緊張から愉快な状態へ移る過渡期である。私の考えるところでは、美が涙を誘う主な理由は、泣く人の性格にある。それは人一倍傷つきやすい人、または感情を抑えている人、または普通以上に神経の張り詰めている人である。毎日の生活から受ける沢山の小さい傷や外に現わさない悲しみをこの人は心に秘めているに違いない。すると突然美に接して、喜びと解放とやさしい情熱がほとばしり出る。障壁は取り除かれて、積り積った悲喜交々の涙が流れだすのである。
怒りとか、恐怖とか、急激な悲しみの衝撃によって、体の中には生理的な変化が起こる。消化作用は低下し、血圧は上がり、心臓は鼓動を速め、皮膚は冷たくなる。これが長く続くと、この異常事態で体が・・そして人間が・・堅く、乾燥して、硬直してしまう。苦しい時に感情を発散させることをはばかるような人では、抑圧された涙がゼンソク、偏頭痛その他の病気を起こす原因になると医師は認めている。
この反対で、涙を流すと、驚きとか衝撃とかいった状態が逆転する助けになる。だから、涙は神経の崩壊とか悪化などのしるしではなくて、暖かさと希望と健康へ向かう週渡期を示すのである。
これは人に先立たれる場合などに、はっきりと現われる。ある若い看護婦が非常に愛していた父親の死病の床に就いたのを看護して、数ヶ月もの間いつも涙を見せまいと我慢しつづけていた。ついに父が死ぬと、母親の気持ちや弱い心臓のことなどを考えたら、決して悲しみを外へ出してはならぬ、と別に悪気もなくきびしく忠言をした人がいた。数時間たつとこの看護婦は腸の工合が悪くなったが、数日たつと急性の潰瘍性大腸炎にかかった。その体は、解放への自然の道をふさがれたので、神経系の衝動の変調が起って次第に内部から侵されたのである。そして終には死んでしまいましたが、感情を抑さえて外に現わすまいとしたために死んだのである。
この反対に、肩の痛みに始まって毎晩のようにうなされていた。それにまだ随分変わったさまざまな病気にかかっていた患者さんが本当に泣いたためにけろっと病気が治ったという例も多い。私の近所のこれも父の患者さんで幾年もの間慢性感冒とその上蓄膿症で悩んでいらっしたが、泣くことで感情を解放する事を覚えると、感冒も蓄膿症もどこかへいってしまったと言ってらした。哲学者は、かつて、我々の情緒は思考力に干渉するもので、情緒を抹殺してしまわないと理解へ達する事が出来ないと考えた。ところが、近代医学によると、我々が感情を抑圧することこそ何にも増して思考力を曇らせる働きをするものだとされている。
それで涙には本当の英知が宿っているわけである――悲しみの涙にも、追憶の涙にも、同情の涙にも、壮大美麗なものに打たれたときの涙にも、激しい喜びの涙にも、これは皆深く根ざした欲求――愛し愛された欲求、怒りや憎しみを投げ出したい欲求、労苦と緊張を洗い流したい欲求等――の現われである。男らしく衝動を抑さえたりせず、自分を泣くままにまかせるならば、私たちは健康への道にふみ出すことになる。英知への道も同様である。涙によって肉体的に解放された状態で初めて、我々の思想の流れは自由自在になるので、自分でとらえ得ると想像もしなかった洞察と理解に達する事が出来るのである。
